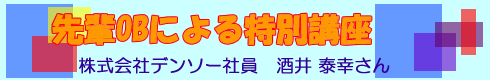便利さと豊かさの陰で摘みとられた知恵と創意工夫の芽、ゆとり教育のツケとして著しい低下を見せる学力―。今の日本の子どもたちに冠せられる評価は、総じて悲観的なものばかり。それならば、日本の子どもたちに、未来の夢は、未知の可能性はないのだろうか?
自動車をはじめ、日本のモノづくり産業を支える街として知られる刈谷市には、日本で最初に誕生した「少年発明クラブ」がある。豊田系企業群のお膝元という有利な地域性を生かし、子どもたちが、さまざまなモノ作り体験に出会える場所として、約30年にわたり機能してきた。既存の学校教育とは一線を画した学習環境の中で、ここにはモノ作りに取り組む子どもたちの、生き生きとした姿があった。
全国で一番最初に誕生した少年発明クラブ。
刈谷駅からほど近い株式会社デンソーの研修施設。その敷地の一角にある、白いコンクリート建物の門塀には、「財団法人豊田理化学研究所 刈谷少年発明クラブ」の表示プレート。研究所さながらの外観が、中から聞こえてくる子どもたちの甲高い声と、不思議な違和感を呈している。
刈谷少年発明クラブの指導員、桑門聰さんがまず最初に案内してくれたのがクラブの展示室。この街の英雄というだけでなく、日本の産業界の礎を築いた豊田佐吉翁の巨大な肖像パネルを背に、クラブの子どもたちの発明した歴代の優秀作品が並ぶ。子どもを対象にした発明大賞は、全国レベルのものから、県、市町村レベルのものまであまたあり、刈谷少年発明クラブは、そうした発明大賞に毎年必ず数点は入賞を果たす日本有数の発明クラブだ。それも、そのはず。このクラブは、今から約30年前の昭和49年、現在は全国で140以上ある発明クラブの中で最初に誕生した、名門中の名門クラブなのだ。豊田系企業9社の出資により設置された財団が運営しており、常勤の7名の講師には、元教員のほか自動車のエアバックなどの研究開発にいそしんだ、かつての一流エンジニアなどが名を連ねている。
講師が一流なら設備も一流だ。建物の地下から3階までの各階には、一般教室のほか、木工室、加工室、機械室など用途別の教室がひしめく。廊下からの様子では、学校の校舎にも似た雰囲気だが、一歩部屋の中に入って思わず息を呑む。多種多様のベニヤ板や釘類といった工作材料のほか、電動糸のこ盤、ハンドドリル、ドライバーをはじめとする道具類も数限りない。モノ作りに必要なありとあらゆるものが完備されている上、数十台のデスクトップが並ぶコンピュータルームまであるのだから、小さな製造工場としてすぐにでも稼動できそうな充実ぶりだ。ただただ驚嘆していると、桑門さんは言った。
「発明クラブは、恵まれた環境で、単発でなく継続してモノ作りの機会を提供できることが魅力です。中学を卒業する頃までに繰り返しモノ作り体験を積んでいけば、自分の頭で考え、自分の手でモノを作れる子が育つはず。そうした自主性や創造性を養う手助けをするのが私たちの役割なんです」。
確かに、設備がどんなに充実していようと、子どもたちに創意工夫する能力、知恵が身につかなければ、すべて宝の持ち腐れである。結局は、彼らの、モノを作る歓びをいかに引き出すというかということが、クラブにとって一番重要であり、最も難しいことなのだ。
豊富に揃う工作材料や道具の数々
「好きなものを自由に作れるのがうれしい」。
クラブは毎週土曜日曜のほか、夏休みは週に4回開かれる。工作の基礎を学ぶ「基礎コース」と中学生を対象にした「上級コース」には定員があるが、クラブの目玉ともいえる「自由工作コース」は、小学4年生からは誰でも入会できる。実際、刈谷市内の小学生の2割に相当する子どもがクラブの会員というから驚きだ。会費はあるが、材料費を含めて年間で千円〜3千円程度という安さ。現在、小学2年生から中学3年生の約900人が会員に登録されていて、去年のデータでは、年間延べ1万人の子どもたちがこのクラブを利用したことになる。夏休みの終わり頃ともなると、クラブは工作の宿題に追われる子どもたちで、連日ごった返すのだそうだ。
一方、ここ数年の間、学校に週休二日制や「総合的な学習の時間」が取り入れられたことで、発明クラブのニーズは多様化した。クラブが、子どもたちにとって学校とは違うかけがえのない居場所としての機能も持つようになったのだ。少なくとも、ここに集う多くの子どもにとって、クラブは生活の一部になっている。
教室を終えた子どもたちに声をかけると、クラブについてそれぞれの思いを語ってくれた。
「学校の授業みたいにこれを作りなさいって言われるんじゃなくて、好きなものを自由に作れるのがうれしい」「ここの先生はいろんなことを知っているから頼りになる」「週に一度は必ず来るけど、ここにいるとあっという間に時間がすぎちゃう」「将来は発明する仕事がしてみたい」。
13年間にわたって刈谷少年発明クラブの運営を取り仕切ってきた鈴木福一会長は、今、クラブのあり方をこんな風に見ている。
「のんびりマイペースで好きなことを思う存分やれる。しかも、宿題や仕事のように納期はない。評価も、ここでは一切しない。親からも学校からもお墨付きの場所だから、誰に気兼ねすることなく来られる。だから多くの子どもが集まってくるんでしょうね。自由な発想や創造力を養う時期にある彼らにとって、こういう場所の意義は大きいと思います。モノ作りの楽しさは、自由な環境でこそ生まれるものですし、ノーベル賞を取るようなすごい発見や発明は、型にはまった人からは生みだされませんからね」。
クラブの終業時間は午後4時。鈴木会長や桑門さんが見送る子どもたちの表情には、確かに、テレビゲームに夢中になる子どもたちにも、塾をはしごする子どもたちにも見られない、生き生きとした充実感のようなものがあった。
刈谷少年発明クラブ
鈴木福一会長
「一時間半のスライドで飽きられると思ったら、意外と食いつきが良かった。子どもたちも、未知の国には興味があるのかな。楽器作りも、普段やっているモーターの工作とは一味違って、楽しかったんでしょうね」と、講義を終え、子どもたちにまとわりつかれる酒井さんは、満足そうに語る。
学生時代はもちろん、社会人になってからは年休を取ってクラブのボランティアで講師をしに来るという酒井さん。
「子どもの頃は、ここに来るのが楽しかった。宝の山でしたからね」。そう笑う今も、クラブは酒井さんにとって「来るとなんだかわくわくする」場所には、変わりないようだ。
先輩OBによる工作教室
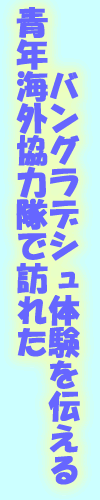
財団法人 豊田理化学研究所 刈谷少年発明クラブ
〒448-0034 愛知県刈谷市神明町 6-401
TEL:0566-23-1161 FAX:0566-25-4765
Email:kshclub@katch.ne.jp
ホームページ:http://www.katch.ne.jp/~kshclub/
財団法人 豊田理化学研究所 ホームページ:
http://www.disclo-koeki.org/02a/00165/index.html
●平成15年度のクラブ会員の募集は、2月12日で締め切られました。